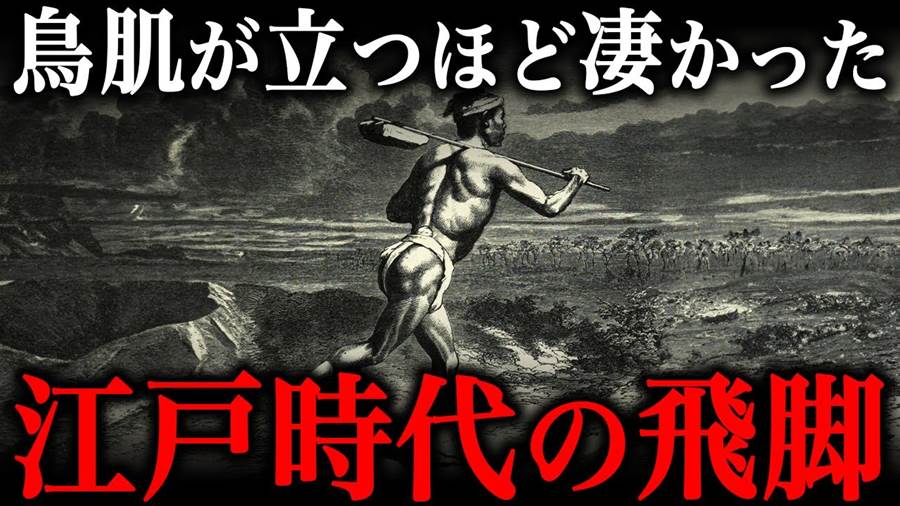
江戸時代の飛脚の実態は、現代の私たちから見ると信じられないほどの過酷さと驚異的な体力を必要としたものでした。特に、江戸から京都までをわずか三日で走破したという話は、まるでフィクションのように感じられます。しかし、これは紛れもない史実です。そして、その裏には飛脚たちが持つ技術と知識、そして社会的な必要性が大きく関わっていました。
飛脚の歴史は鎌倉時代に遡ります。当時、鎌倉幕府が京都との連絡を迅速に行うために、特別に選ばれた俊足の使者を送りました。彼らは「六原飛脚」と呼ばれ、鎌倉から京都までを最短で72時間以内に駆け抜けたとされています。彼らが後の江戸時代の飛脚の原型となりました。

江戸時代に入ると、飛脚は幕府の御用として重要な役割を担うようになります。江戸幕府が全国を統治するためには、迅速な情報伝達が欠かせませんでした。特に、江戸と京都、大阪間の連絡は国家の要となるもので、飛脚がその重要な任務を担いました。
飛脚たちが驚異的なスピードで文書や荷物を運んだ秘密は、「駅伝方式」にありました。これは、複数の飛脚が交代で区間を走る方法です。例えば、一人の飛脚が全行程を走り切るわけではなく、一定の距離ごとに別の飛脚が待機しており、荷物や文書をリレーのように受け渡して次の区間へと運んでいきます。この方式により、飛脚たちは全力疾走で短距離を走ることができ、結果として長距離を驚異的な速さで移動することが可能になりました。
この駅伝方式は、特に幕府の緊急時には大いに活用され、江戸から京都、大阪間を2日から3日で走破するという驚異的な成果を上げたのです。通常ならば、徒歩で30日以上かかるこの距離を、飛脚たちはわずか数日で走破したのです。
飛脚という仕事は、ただ俊足であれば務まるものではありませんでした。彼らには強靭な体力が求められ、厳しい自然環境や悪天候の中でも使命を全うする精神力が必要でした。飛脚たちは道中の宿や食事もままならない中、汗だくになりながら峠を越え、川を渡り、山を登り続けました。
昼夜を問わず、少しでも早く目的地に到達するため、過酷な環境に身を置くことは当たり前でした。

飛脚は、公式な文書や大名の命令書を運ぶだけでなく、民間からの依頼にも応じていました。商人や庶民が江戸、大阪間で手紙や荷物を送る際には、飛脚の存在は欠かせませんでした。しかし、その運賃は非常に高額で、特に急ぎの「特急便」を利用する場合には、現代の価値で45万円にも達することがあったそうです。庶民には手が届かないサービスだったため、通常の便であれば30日程度かけて荷物が届けられることが一般的でした。
江戸時代を通じて重要な役割を果たしてきた飛脚も、明治時代に入ると時代の波に押され、次第に姿を消していきました。特に1871年(明治4年)の郵便制度の導入により、国家主導での通信網が整備され、飛脚の役割は徐々に郵便事業へと取って代わられました。郵便制度の整備により、全国的に信頼性の高い通信手段が確立され、飛脚という職業はその役割を終えることとなったのです。
しかし、飛脚が築き上げた迅速な輸送システムや、顧客の要望に応じた柔軟な対応は、後の物流業界に大きな影響を与えました。現代の宅配便システムの根底には、飛脚たちが築き上げた迅速かつ確実な輸送技術が受け継がれていると言っても過言ではありません。

江戸時代の飛脚たちは、まさに「アスリート」と呼ぶにふさわしい存在でした。彼らの驚異的な体力と忍耐力、そして迅速に情報を伝達する使命感は、現代の物流業界にも通じるものがあります。飛脚という職業は、江戸時代の社会を支える重要な要素であり、その存在なくしては当時の日本は成り立たなかったと言えるでしょう。彼らの足跡は、今もなお私たちの生活に深く影響を与え続けています。
引用元:https://www.youtube.com/watch?v=PvbQo6iKF5g,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]








