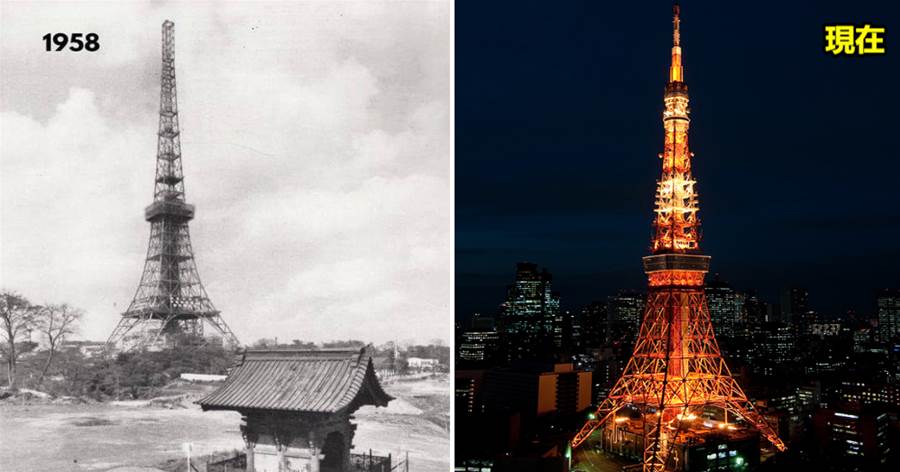昭和33年、私の両親は結婚し、新婚旅行に出かけました。当時、若々しい二人は29歳の父と23歳の母。彼らが選んだ旅先は、南紀白浜、勝浦、新宮という和歌山の名所でした。関西出身の両親にとって、旅行先としては京都や奈良、伊勢志摩も一般的な選択肢だったにもかかわらず、なぜ南紀を選んだのか、その理由には当時の人々の間にあった憧れや、それにまつわる一つの深い思い出がありました。
南紀白浜といえば、美しい海岸線と豊かな自然、そして温泉地としても有名です。当時の新婚旅行の定番コースでもありましたが、特に白浜は「若者のリゾート」としてその名を馳せていました。だからこそ、若い二人にとってはぴったりの選択だったのでしょう。しかし、一枚の写真が目を引くのは、旅行先そのものではなく、母の着物姿です。
現代であれば、リゾート地に出かける際は洋装やカジュアルな服装が一般的ですが、昭和の時代、特に戦後の日本ではまだまだ着物が普段着として根付いていた時代でした。それでも、新婚旅行に着物を選ぶことは珍しいことでした。母はなぜこの特別な旅行で着物を選んだのか。その答えは、母自身が語らないままでしたが、いくつかの推測を立てることはできます。

ひとつは、当時の日本女性が持っていた「凛とした美しさ」へのこだわりです。母は、若いながらも芯の強い女性で、いつも慎ましさと品を重んじていました。新婚旅行という特別な時だからこそ、フォーマルな装いである着物を選んだのかもしれません。白浜の開放的な風景の中に佇む母の姿は、まるでその地の風景に溶け込むかのように優雅で、見る者を魅了します。
もうひとつ考えられる理由は、戦後の日本社会における「新しい時代」と「古き良き時代」の狭間に生きた彼女の世代特有の感覚です。戦争が終わり、日本は高度経済成長期に向かっていましたが、その中でも昔ながらの価値観や美意識は強く残っていました。母が着物を着ていたのは、そんな変わりゆく時代に対する敬意と、自分のルーツを大切にする気持ちだったのかもしれません。着物は日本の伝統的な衣装であり、特に女性にとっては自身のアイデンティティを表現する手段でもありました。
それに対して、父は洋装を選びました。
これも当時の象徴的な姿といえます。日本が戦後、急速に西洋化していく中で、男性はスーツやネクタイといった洋装が主流となっていきました。父はその象徴的な姿で、母の横に並び、まるで新しい日本と伝統が手を取り合って未来に向かって歩んでいるかのような風景を作り出しています。
そして、この新婚旅行には、家族にとって大切なもう一つの意味がありました。両親が結婚した昭和33年というのは、日本にとって大きな転換点でもありました。戦後の復興が進み、生活も徐々に豊かになっていく中で、人々は新たな希望とともに日常を過ごしていました。二人にとっても、この旅行は単なる結婚のお祝いではなく、これから二人で築いていく未来に向けての最初のステップだったのでしょう。
その後、両親は家庭を築き、私たち子供たちを育て上げました。しかし、母がなぜこの新婚旅行で着物を選んだのか、その真相は未だに謎のままです。時折、母に聞いてみたくなることもありますが、その理由を想像するだけでも、当時の母の心の中を垣間見ることができるような気がして、あえて聞かないままにしているのです。
今になって思い返すと、この新婚旅行の写真は、ただの一枚の記念写真ではありません。
それは、私たち家族にとっての出発点であり、両親の若さや希望、そして覚悟が詰まった特別な瞬間の証です。父の堂々とした姿と、母の優雅な着物姿が一緒に収められたこの写真を見るたびに、彼らがどれだけ強い絆で結ばれていたのかを改めて感じることができます。

こうして振り返ると、南紀白浜を選んだ理由も、着物姿での旅行も、ただの偶然ではなく、二人にとって意味のある選択だったのかもしれません。その選択が、今でも家族にとっての大切な思い出となっているのです。結果的に、この写真は私たち家族にとって、未来を象徴する宝物となりました。
感動的な結末として、両親が選んだ道は、まさに人生の旅そのものでした。彼らが歩んだ道は、時には険しく、時には穏やかであったでしょう。しかし、この写真が示す通り、どんな困難があっても、二人で支え合い、未来を切り拓いていくという強い意志がそこにはあったのです。