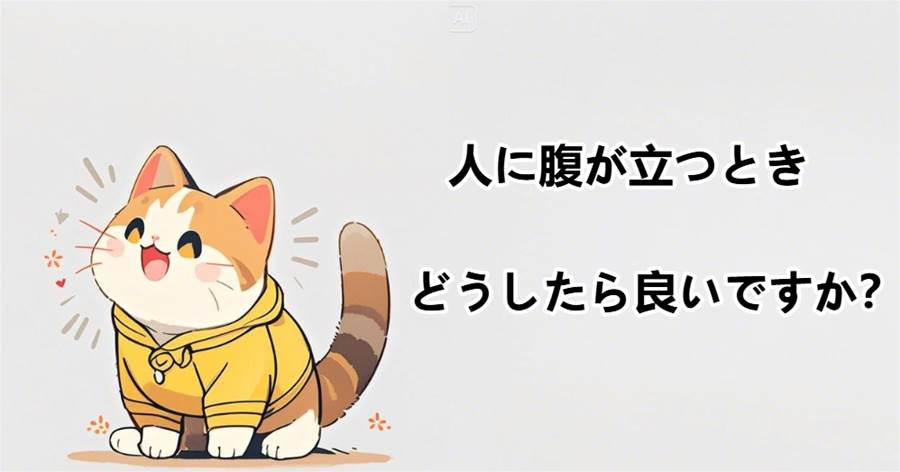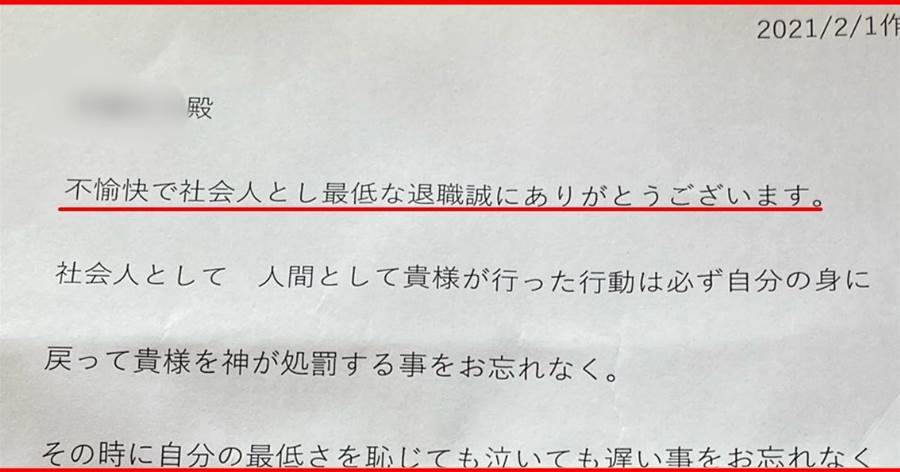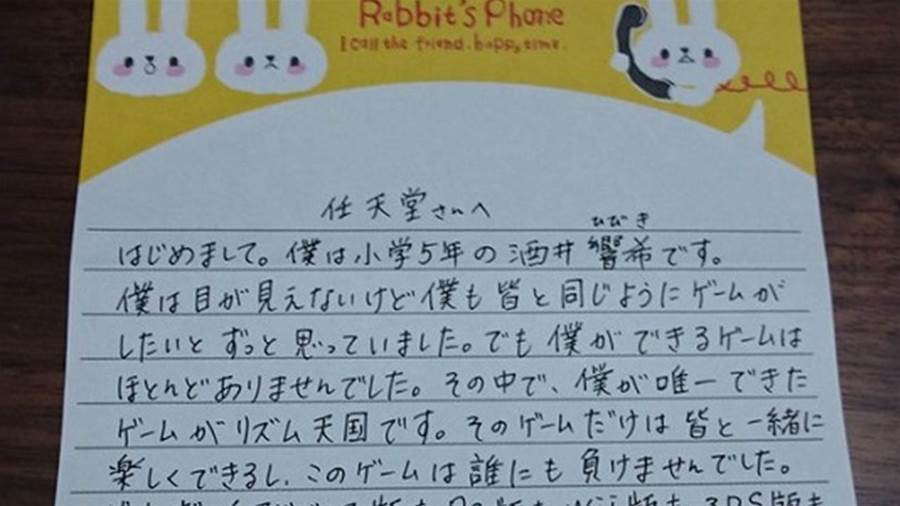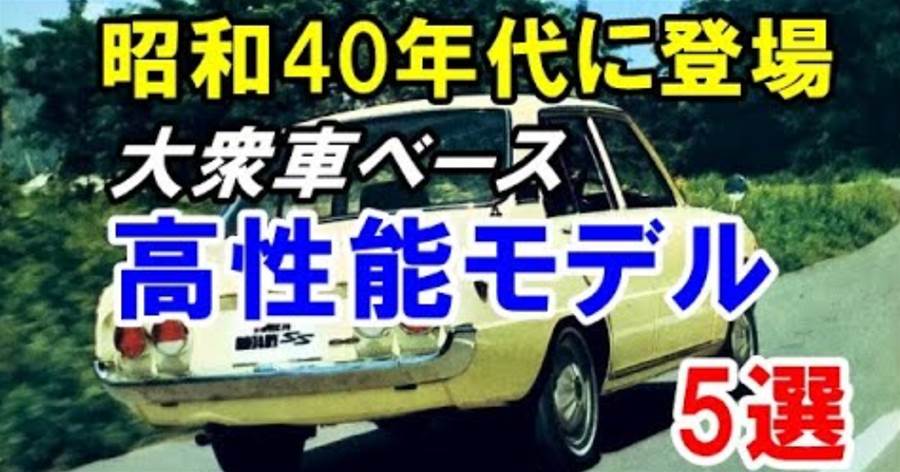
昭和40年代、日本は高度経済成長の真っただ中にあり、自家用車の普及が進んでいました。カローラやサニーといった大衆車が誕生し、手頃な価格で庶民にも車を持つことができる時代が訪れたのです。そんな中、これらの大衆車の中にも高性能なモデルが登場し、若者たちに圧倒的な支持を集めました。
今回は、当時登場した大衆車ベースの高性能モデル5選をご紹介いたします。ロータリーエンジンやDOHCエンジンなど、革新的な技術が投入された名車たちに迫ります。
まず紹介するのは、1967年に登場したマツダの2代目ファミリアです。当初は1リッターのエンジンを搭載したシンプルな大衆車でしたが、翌年にマツダの象徴であるロータリーエンジンを搭載した「ファミリアロータリークーペ」が登場します。

このロータリーエンジンは、最高出力100馬力を発揮し、最高速度は180キロにも達する驚異的なスペックを誇っていました。
見た目は一般的なセダンながら、その走行性能はまさに「羊の皮をかぶった狼」と評されるにふさわしいものでした。専用の三角形エンブレムや丸型テールランプなどでベースモデルと差別化が図られ、以降、マツダのロータリーエンジン車は「高性能の象徴」として支持を集めていきました。
1970年に登場した日産の2代目サニー。ボクシーなデザインのボディに1.2リッターのエンジンを搭載し、軽快な走りが魅力の一台でした。しかし、このモデルにはさらにスポーティーな「1200GX」グレードが設定され、ツインキャブを備えたエンジンにより83馬力を発揮。軽量ボディとの組み合わせでツーリングカーレースでも高いパフォーマンスを見せました。
2年後には5速MTを搭載した「GX5」も追加され、このサニーは単なる大衆車ではなく、若者たちが熱狂するスポーツモデルとしての一面を持つようになりました。2代目サニーは、日産のスポーツセダンの歴史においても重要な位置を占める一台となったのです。

1970年に2代目となったカローラとスプリンターは、互いに兄弟車として並んで登場しました。スポーティーなデザインが特徴のスプリンターは、特に若者層をターゲットにしており、ツインキャブ仕様の1.4リッターエンジンを搭載したことで軽快な走りを実現していました。
さらに1972年には1.6リッターのDOHCエンジンを搭載した「カローラレビン」「スプリンタートレノ」が追加され、最高出力115馬力という当時としては驚異的なパワーを誇りました。オーバーフェンダーやラジアルタイヤが装備され、精悍なルックスも人気を呼びました。このレビンとトレノは、後に続くスポーツカー市場を牽引する存在として、多くの若者を虜にしたのです。
1972年に登場したホンダの初代シビックは、軽量でありながら広い室内空間を確保し、当時の日本車には珍しいFFツーボックスカーという新しいスタイルを採用しました。
経済性重視のシンプルな設計でしたが、1974年にスポーツモデル「シビックRS」が登場。最高出力76馬力のエンジンを搭載し、軽快な加速と鋭いレスポンスを実現しました。
また、スポーツシートやウッド製のステアリングホイールを標準装備し、細部に至るまでスポーティさを追求。ホンダらしい「走りの楽しさ」を具現化したシビックRSは、日本のホットハッチの先駆けとして、多くのファンに愛されました。
1973年に登場した三菱の初代ランサーは、カローラやサニーに対抗するためのモデルとして開発されました。しかし、8月に追加された「ランサー1600GSR」は、ラリー競技のベース車両としての一面を持ち、最高出力110馬力のエンジンを搭載。軽量ボディに加えてラリーに対応した足回りを持ち、サファリラリーでの優勝をはじめとする国際ラリーでの活躍が評価されました。

この1600GSRの成功によって、ランサーは単なるファミリーカーではなく、走行性能が高く評価されるモデルとしての地位を確立しました。1975年にはさらにスポーティなクーペバージョンの「ランサーセレステ」が登場し、ランサーシリーズのスポーツカーとしての魅力を強調しました。
結び
以上、昭和40年代に登場した大衆車ベースの高性能モデル5選をご紹介しました。これらのモデルは、当時の日本の自動車産業の成長とともに進化し、単なる大衆車から「走る楽しさ」を提供する高性能モデルへと変貌を遂げたのです。これらの車たちが、現在のスポーツカーブームの礎を築いたと言っても過言ではありません。
引用元:https://www.youtube.com/watch?v=B2uHqVNU32o,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]